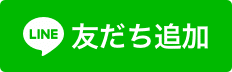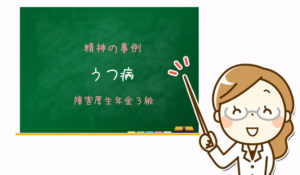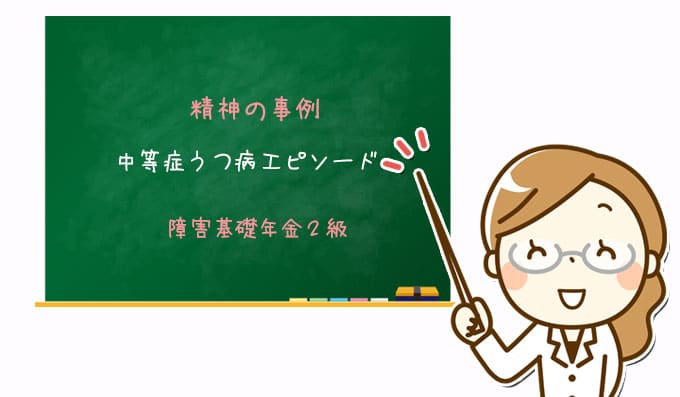
うつ病で障害年金を申請される場合の注意点などは『【社労士が解説】うつ病で障害年金を申請するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。
目次
対象者の基本データ
| 病名 | 中等症うつ病エピソード(広汎性発達障害) |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 支給額 | 年額 約78万円 |
| 障害の状態 | ・人の少ない夜間の時間帯に限って、短時間就労を行っている ・他の従業員とのコミュニケーションは図れず、特定の上司とペアでなければ勤務できない ・食事や掃除、洗濯、買い物等の日常生活の大半をヘルパーさんに頼っている ・精神障害者保健福祉手帳3級 |
| 申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
幼少期より対人関係で悩むことが多かったそうです。
高校卒業後は就職、結婚し子供も出産しましたが、育児がうまくできず、子供に手を出してしまうこともありました。
職場では対人関係をうまく築くことが出来ず、短期間での転職を繰り返していました。
ただ、発達障害という認識はなく、医療機関を受診することはありませんでした。
40代になり、家庭も仕事も立ち行かなくなり、不眠や抑うつ気分、希死念慮を自覚するようになり、病院を受診。
「広汎性発達障害」と診断されました。
定期的に通院を継続し、初診日から1年半経過した日頃に障害年金を申請しましたが、結果は不支給。
不支給となってしまったことで気分も落ち込み、障害年金の受給は諦めていました。
その後も症状は徐々に悪化し、発達障害の二次障害として「うつ病」と診断を受け、現在も治療を継続しています。
生活が立ち行かない状況から生活介助の為ヘルパー利用を始めました。
過去に一度不支給となっていますが、ご本人の現在の生活状況からして障害年金が受給できるのではないかと担当のヘルパーさんから当事務所にご相談をいただきました。
申請結果
今回は2回目の申請となりますので、前回の不支給原因の追究と申請方針の検討の為、過去申請書類の取り寄せ(個人情報の開示請求)から手続きを始めました。(ポイント①)
過去申請書類の内容を確認すると初診日の証明は問題なかったものの、医師の診断書とご本人様の作成された病歴就労状況等申立書の内容に整合性のない点が点在していること、また病歴就労状況等申立書の記載内容も申請傷病に関する論点とはやや相違した内容となっており、実際の日常生活における支障の程度が審査認定医にうまく伝わっていなかったことが要因として考えられました。
その為、初診日の証明は前回申請書類のものを再利用し、障害状態の確認で重要となる診断書と病歴就労状況等申立書の内容が現在のご本人様の状況に沿ったものとなるように申請書類を作成していく方針としました。
2回目の申請時現在は初回申請時とは異なり、「うつ病」の診断を受けている為、前回申請時から現在に至るまでの経過や症状、日常生活状況等について改めてヒアリングさせていただき、ヒアリングした内容を基に参考資料を作成し、診断書を作成していただく医師へ橋渡しを行いました。
また、診断書の記載内容だけでは伝わりにくい実際の就労や日常生活への支障については病歴就労状況等申立書にて補足し、診断書との整合性も意識して書類の作成を行いました。
申請の結果、「障害基礎年金2級」として認定されました。
今回の事例のように過去に一度不支給となっても再度申請して認めてもらえるケースもあります。(ポイント②)
不支給となっても諦めずに一度専門家へご相談ください。
【ポイント1】個人情報の開示請求
障害年金を申請して不支給になった場合や支給決定を得られたものの納得のいく等級が得られなかった場合に、再度一から裁定請求や審査請求を検討していくこととなります。
決定内容には何らかの理由があって決定がなされていますので、「なぜそのような決定になったのか」その理由を知り、再度の裁定請求や審査請求に臨むことが大切です。
その理由を知る方法の一つに「個人情報開示請求」を行い、認定調書の写しを入手する方法があります。
個人情報の開示請求は厚生労働大臣宛てで行います。
手続きの方法や流れは下記URLをご参照ください。
【ポイント2】一度不支給となっていても受給の可能性あり
過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。
大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。
原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。
その他のうつ病の事例
当事務所で申請サポートさせて頂いた、その他のうつ病の方の事例をご紹介します。
うつ病の新着事例
よく読まれるうつ病の事例
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら
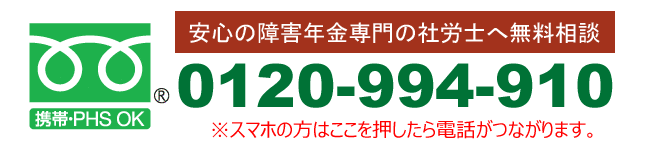
LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。