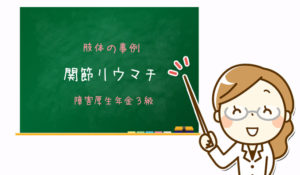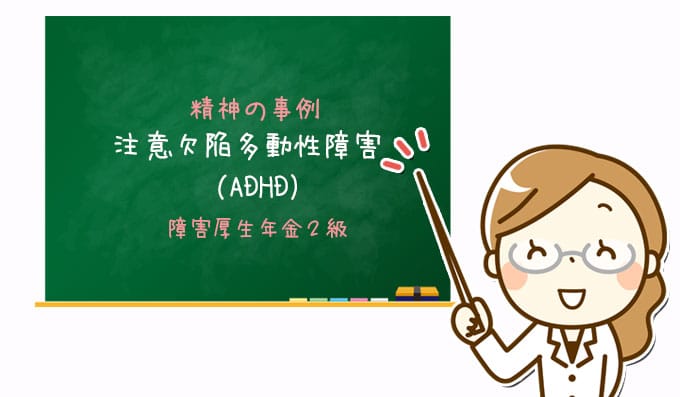
目次
対象者の基本データ
| 病名 | 注意欠陥多動性障害(ADHD) |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 支給額 | 年額 約109万円 遡及金額 約41万円 |
| 障害の状態 | ・物事の段取りや優先順位付けが難しいため、食事の準備や掃除などの家事が計画的に進められず、生活環境が乱れがち ・必要なものを忘れる、紛失することが頻繁にあり、生活がスムーズに進まない ・適切な言葉選びや会話の流れを掴めず、円滑な意思疎通が困難 ・精神障害者保健福祉手帳3級 |
| 申請結果 | 障害厚生年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は幼少期から発達特性がありましたが、自身が発達障害であるという認識はなく、医療機関を受診することもなく成長されました。
大人になり、社会人として働く中でリーダー職に抜擢されましたが、業務の段取りを組むことが難しく、部下への指示も思うようにできなくなりました。
次第に抑うつ症状が現れ、不安が強くなったため、初めて病院を受診されました。
診断の結果、「注意欠陥多動性障害(ADHD)」と「うつ病」が判明し、発達障害が根底にあり、二次的にうつ病が生じていると診断されました。
その後も通院を続けながら就労されましたが、症状が改善せず、最終的には退職。
退職後は就労移行支援事業所を利用し、その後、障害者雇用枠で就職されました。
申請結果
ご依頼者様のご希望もあり、「障害認定日請求(遡りの請求)」にて申請を進めることとなりました。
障害認定日から請求日現在時点で既に1年以上経過しているため、診断書は初診日から1年6か月経過した日頃の障害認定日時点のものを1通、請求日現在時点のものを1通の合計2通取得しました。
完成した診断書の内容はそれぞれ以下のような内容でした。
1)障害認定日時点の診断書
・無職で、就労移行支援事業所に通所中
・日常生活能力はガイドラインの目安上、2級相当
2)請求日現在時点の診断書
・一般企業にて障害者雇用枠で就労しており、約3年勤務継続中
・日常生活能力はガイドラインの目安上、2級相当
上記診断書に記載された内容以外の要素として、診断書を作成して頂いた日時点では勤務継続中でしたが、年金機構への申請日時点ではうつ病の悪化により休職されており、この点も審査上考慮される可能性があると考え、別途申立書類に記載を行いました。
障害認定日時点では、ガイドラインの目安通り2級に認定される可能性があると思われましたが、請求日現在時点では障害者雇用で3年以上継続就労されていたことから、ガイドラインの目安と異なる等級に認定される可能性も予測されました。
事実、過去の事例でも、障害者雇用での就労であっても厳しく判断されているケースがあり、特に障害厚生年金の請求ではガイドラインの目安上では2級でも就労状況を踏まえて3級での認定となるケースもあり、今回の事例においても同様のケースが考えられました。
結果
申請の結果、障害認定日・事後重症ともに2級で認定されました。
認定において考慮されたと考えられるポイント
- 発達障害が根底にあり、うつ病が二次的に発症しており、それぞれの傷病による制限支障を考慮し、総合的に判断されたこと
- 勤務継続のために、障害者雇用で相当程度の援助をうけて就労していること
- 請求日時点において、うつ病の増悪により休職に入っていたこと(以前にもうつ病の病状により休職を繰り返していた経過もあること)
過去の事例では、うつ病のみの場合は3級や不支給になることもありました。
しかし、ご依頼者様の場合、発達障害だけではなく、うつ病が併発していることもあり、発達障害による「認知機能の問題」「作業の指示理解が難しい」「突発的な変更への対応が困難」などの支障が継続しているため、相当程度の援助がなければ継続就労は難しい状態であり、なおかつ、発達障害の二次障害としてうつ病も併発していることによる支障制限の程度も顕著であることが審査においても考慮され、今回の決定に繋がったのではないかと思われました。
感想
最近の審査傾向として、精神の障害年金では就労状況が厳しく審査される傾向にあります。
しかし、今回のケースでは、
- 発達障害による根本的な支障や制限
- 二次的に生じているうつ病による就労・生活の不安定さ
- 障害者雇用での制限付き就労で、休職期間もある
これらが総合的に考慮されたことで、ガイドラインの目安通り2級認定につながったと考えられます。
「発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定する」という障害認定基準に即した適正な審査が具現化された事例となりました。
結果が出た後、審査の詳細を確認するため、認定調書を取得したところ、休職の経過についても審査上考慮されていたことが確認できました。
障害年金の審査は書面審査のため、「申請傷病によって、どのような支障制限があるのか」を的確に申請書類に反映することが重要であると改めて感じました。
特に医師の診断書は審査上重要な資料の1つとされるため、診断書作成は医師に丸投げではなく、適正な審査を受けるためにも主治医の先生に必要な情報提供を行うことが大切だと考えます。
【ポイント1】発達障害と就労
発達障害の中でも、大人になって社会に出てから生きづらさを感じ発達障害と分かるケースが増えています。
このようなケースでの障害年金は、最近では2級以上の認定は難しい傾向にあります。
ただし、これはあくまでも傾向であるため、専門家へのご自身の症状を伝えて相談を行う事をオススメします。
なお、障害年金と就労の関係について以下の動画でも詳しく解説をしています。
【ポイント2】医師は診断書を書くプロではない
医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。
とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。
そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。
【ポイント3】診断書(精神の障害用)
精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。
診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。
診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。
伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。
以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。
その他の注意欠陥多動性障害(ADHD)の事例
その他の発達障害の事例
当事務所で申請サポートさせて頂いた、その他の発達障害の方の事例をご紹介します。
発達障害の新着事例
よく読まれる発達障害の事例
わくわく社労士法人が選ばれる理由
2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)
【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
(匿名様からのご感想)

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
(匿名様からのご感想)
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら
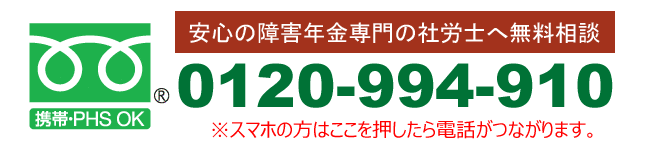
LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。
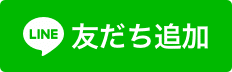

.jpg)