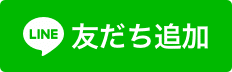今この記事を読んでくださっている方の中には、うつ病を患って「働きたくても、心が悲鳴を上げて体が動かない」「休んでいても、減っていく預金通帳を見るたびに焦りが募り、夜も眠れない」・・・そんな日々を過ごされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、どうか安心してください。
日本には、病気やケガで働けなくなったあなたを社会全体で支えるための、いくつもの公的な支援制度が用意されています。
これらの制度は、あなたが受け取るべき正当な権利です。
ただ、制度の仕組みは複雑で、どこに相談すれば良いのか、自分はどの制度を使えるのかが分からず、途方に暮れてしまう方が多いのも事実です。
この記事は、うつ病で働けず、お金の心配をされている方が利用できる公的制度を、一つひとつ丁寧に、そして分かりやすく解説していきます。
目次
「現在の状況」を把握する
利用できる制度を具体的に見ていく前に、最も大切なことから始めましょう。
それは、ご自身の「現在の状況」を正確に把握することです。
なぜなら、あなたが今「会社に在籍しているか、していないか」によって、利用できる制度が大きく変わってくるからです。
この最初のボタンを掛け違えてしまうと、本来受け取れるはずだった支援が受けられなくなる可能性さえあります。
まずは下の表で、ご自身の状況を確認し、どの章から読み進めるべきかを見つけてください。
表1: あなたの状況別・使える制度
| あなたの今の状況は? | 最初に検討すべき制度 | まず読んでいただきたい章 |
| 【会社に在籍中】 休職している、または休職を考えている | 傷病手当金 (休職中の生活を支える最も重要な制度です) | 【休職中の方へ】会社に在籍しながら生活を支える制度 |
| 【会社に在籍中】 働きながら治療しているが、限界を感じている | 傷病手当金 (退職する前に、まず休職して傷病手当金を受給できないか検討することが非常に重要です) | 【休職中の方へ】会社に在籍しながら生活を支える制度 【退職された方・退職を検討中の方へ】離職後の生活を守る制度 (休職と退職、それぞれの選択肢を慎重に比較検討してください) |
| 【退職済み】 体調は回復傾向にあり、就職活動ができる状態 | 失業手当(雇用保険) (うつ病が理由の退職は、有利な条件で受給できる可能性があります) | 【退職された方・退職を検討中の方へ】離職後の生活を守る制度 |
| 【退職済み】 療養が必要で、すぐに就職活動はできない状態 | 障害年金 (長期的な療養生活を支える大きな柱となります) 傷病手当金の継続給付 (退職時に傷病手当金を受給していた場合) | 【長期的な療養が必要な方へ】障害年金という、もう一つの大きな支え |
| 【すべての方向け】 医療費や税金の負担を減らしたい 収入が途絶え、生活が極めて困難 | 自立支援医療制度、精神障害者保健福祉手帳 生活保護 | 収入確保と負担軽減のために使える制度 |
ご自身の状況が確認できましたら、該当する章からじっくりと読み進めていきましょう。
もちろん、全体を読んでいただくことで、利用できる制度の全体像をより深く理解することができます。
【休職中の方】会社に在籍しながら生活を支える制度
現在、会社に籍を置いたまま休職されている方、あるいは休職を検討されている方にとって、最も重要となるのが「傷病手当金」です。
まずはこの制度をしっかりと理解し、活用することが、安心して療養に専念するための第一歩となります。
傷病手当金

傷病手当金とは、会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入している方が、業務外の病気やケガ(うつ病も含まれます)のために仕事を休み、会社から給与が十分に支払われない場合に、ご本人とそのご家族の生活を保障するために支給されるお金です。
もらえる金額は?
傷病手当金として1日あたりに支給される金額は、大まかに言うと「お給料の約3分の2」です。
正確な計算式は以下の通りです。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×(⅔)
少し複雑に聞こえるかもしれませんが、例えば、休職前の1年間の給与(賞与は除く)の平均が月30万円だった場合、1日あたりの支給額は300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約6,667円となります。
これが、休んだ日数分支給されることになります。
もらえる期間は?
支給される期間は、支給を開始した日から「通算して1年6ヶ月」です。
この「通算して」という点が非常に重要です。
以前は、支給開始から1年6ヶ月が経過すると、途中で復職した期間があってもそこで支給は終了してしまっていました。
しかし、制度が改正され、現在は、支給期間が通算されるようになりました。
つまり、一度復職して給与が支払われた期間はカウントがストップし、もし再び同じ病気で休むことになった場合、残りの期間分の傷病手当金をまた受け取ることができるのです。
この制度改正は、症状に波があり、復職と休職を繰り返す可能性のあるうつ病の方にとって、非常に心強いものと言えるでしょう。
受給するための4つの条件
傷病手当金を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
業務外の病気やケガによる療養であること
うつ病ももちろん対象です。
ただし、仕事の過重労働やハラスメントなどが原因でうつ病になったと認められる場合は、次に説明する「労災保険」の対象となる可能性があります。
療養のために仕事ができないこと(労務不能)
これはご自身の判断ではなく、「医師が労務不能である」と証明する必要があります。
医師の診断書が重要になります。自宅療養でも対象となります。
連続して3日間会社を休んでいること(待期期間)
支給が開始されるのは、連続して3日間休んだ後の「4日目」からです。
この最初の3日間を「待期期間」と呼び、この期間は支給対象になりません。
有給休暇や土日祝日でも待期期間に含めることができますが、とにかく「連続して3日間」休んでいることが必要です。
例えば、2日休んで1日出勤し、また休んだ、という場合は待期が完成しないため注意が必要です。
休んでいる期間、会社から給与の支払いがないこと
休職中に会社から給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、支払われる給与の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
申請手続きの流れ
申請は、一般的に1ヶ月単位で行います。
給与の締め日が過ぎてから、その月分の申請をするのがスムーズです。
- 申請書の入手:ご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトから「傷病手当金支給申請書」をダウンロードするか、会社の担当部署に依頼して入手します。
- 本人記入欄の作成:申請書の被保険者(本人)が記入するページに、氏名や振込先口座などを記入します。
- 会社に証明を依頼:申請書には、事業主が休んだ期間や給与の支払状況を証明する欄があります。会社の担当部署(人事部や総務部など)に記入を依頼します。
- 医師に意見を依頼:主治医に、労務不能であった期間や症状について証明してもらう欄があります。医療機関の窓口で作成を依頼します。
- 提出:すべての記入が終わったら、健康保険組合や協会けんぽに提出します。会社経由で提出する場合と、ご自身で郵送する場合がありますので、会社の担当者に確認しましょう。
退職後も傷病手当金を受け取る方法(継続給付)
ここが非常に重要なポイントです。
うつ病の療養が長引き、休職期間満了などでやむを得ず退職することになった場合でも、一定の条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取ることができます。
これを「資格喪失後の継続給付」と呼びます。
その条件は以下の2つです。
- 退職日までに、継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること
- 退職日に、現に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること
つまり、退職する前に、まず休職して傷病手当金の受給を始めておくことが、退職後の生活を守る上で極めて重要になるのです。
心身ともに限界で「もう辞めたい」と衝動的に退職届を出してしまうと、この継続給付の権利を失ってしまう可能性があります。
退職という大きな決断をする前に、まずは休職という選択肢をとり、傷病手当金を確保することが、あなたに経済的な余裕と、今後の選択肢の幅をもたらしてくれます。
これは専門家として、最も強くお伝えしたい点です。
労災保険
もし、あなたのうつ病が、長時間労働、セクハラやパワハラといった、明らかに仕事が原因で発症したものである場合、「労働災害(労災)」として認定される可能性があります。
労災と認定されると、傷病手当金の代わりに労災保険から「休業(補償)給付」が支給されます。
また、治療費は原則自己負担がなくなります。
労災保険の休業補償給付は仕事中や通勤中に起きた怪我や病気に対して給付されるのに対し、健康保険の傷病手当金は仕事以外が原因の怪我や病気の場合に支払われるため、同じ怪我や病気で労災保険と傷病手当金の両方から給付を受け取ることはできません。
なお、労災の認定を受けるには、精神障害と業務との間に明確な因果関係があることを証明する必要があり、その手続きは複雑で時間もかかることが多いです。
もし「自分のうつ病は仕事が原因かもしれない」と感じる場合は、労働基準監督署や、労働問題に詳しい弁護士、社会保険労務士などの専門家に一度相談してみることをお勧めします。
【退職された方・退職を検討中の方】離職後の生活を守る制度

すでに会社を退職された方、あるいは退職を考えている方が次に検討すべき制度が「失業手当(雇用保険)」です。
ただし、この制度は「働ける状態にあること」が前提となるため、うつ病の方にとっては少し注意が必要です。
失業手当(雇用保険)
失業手当(正式には雇用保険の基本手当)は、会社を辞めた方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職するための支援として支給されるものです。
「働ける」状態とは?
まず大前提として、失業手当は「失業の状態」にある方のための制度です。
「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」を指します。
ここで「うつ病で療養中の自分は対象外なのでは?」と不安に思うかもしれません。
確かに、症状が重く、医師から就労を止められており、とても求職活動ができない状態では、この条件を満たさず、失業手当は受給できません。
しかし、「働ける能力がある」とは「うつ病が完全に治った状態」を意味するわけではありません。
「治療を続けながらも、体調が安定し、ハローワークに通って求職活動を行うことができる状態」であれば、受給の対象となり得ます。
この点が、うつ病の方が失業手当を利用する上での重要なポイントです。
【重要】「特定理由離職者」「就職困難者」という有利な区分
自己都合で退職した場合、失業手当の受給資格決定日から7日間の待機期間満了後までに1~3ヶ月間は失業手当が支給されない「給付制限」という待機期間があり、給付日数も比較的短くなります。
しかし、うつ病などの「正当な理由」があってやむを得ず退職した場合は、ハローワークで「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
さらに、うつ病などの障害によって就職が著しく困難であると判断された場合は、「就職困難者」という区分に認定されることがあります。
これらの区分に認定されると、給付制限がなくなったり、給付日数が大幅に増えたりと、非常に有利な条件で失業手当を受け取ることができます。
この認定を受けるためには、ハローワークでの手続きの際に、うつ病であることを証明する医師の診断書や意見書を提出することが不可欠です。
具体的にどれくらい有利になるのか、下の表で比較してみましょう。
表2: 失業手当の受給資格 徹底比較表
| 項目 | ①一般の離職者 (正当な理由のない自己都合退職) | ②特定理由離職者 (うつ病など正当な理由あり) | ③就職困難者 (うつ病などで就職が困難) |
|---|---|---|---|
| 給付制限期間 | 原則1ヶ月あり | なし | なし ※「病気で働けなくなった」などの正当な理由があって退職した場合のみ |
| 所定給付日数 | 90日~150日 | 90日~330日 | 150日~360日 |
| 必要な被保険者期間 | 離職日以前2年間に12ヶ月以上 | 離職日以前1年間に6ヶ月以上 | 離職日以前1年間に6ヶ月以上 ※「病気で働けなくなった」などの正当な理由があって退職した場合のみ |
この表からわかるように、「特定理由離職者」や「就職困難者」に認定されるかどうかで、受け取れる金額や期間に大きな差が出ます。
特に「就職困難者」と認定されれば、被保険者期間が1年以上で45歳未満の場合、給付日数が300日にもなります。
退職後の生活を立て直す上で、これは計り知れないほどの大きな支えとなります。
諦めずに、医師に相談の上、ハローワークで適切な手続きを行いましょう。
すぐに働けない場合は「受給期間の延長」を
退職後、うつ病の症状が重く、すぐに求職活動を始められないという方も多いでしょう。
その場合は、「受給期間の延長」手続きを必ず行ってください。
失業手当は、原則として退職日の翌日から1年以内に受け取り終えなければなりませんが、病気などの理由ですぐに働けない場合は、申請することでその期間を最大で3年間延長し、合計4年間にすることができます。
これにより、まずは療養に専念し、体調が回復してから、ゆっくりと失業手当を受けながら再就職活動を始める、ということが可能になります。
延長の申請は、退職後30日を過ぎてから、なるべく早くお住まいのハローワークで行う必要があります。
傷病手当金と失業手当の併給は?
結論から言うと、傷病手当金と失業手当を同時に受け取ることはできません。
これは、二つの制度の目的が根本的に異なるためです。
- 傷病手当金:病気やケガで「働けない」人のための制度
- 失業手当:「働ける」状態にあるが、仕事がない人のための制度
この二つは、定義上、両立しないのです。
では、どうすればよいのでしょうか。正しい順序は以下の通りです。
- まずは傷病手当金で療養に専念する:退職後も傷病手当金の継続給付を受けている方は、まずそちらを最大限活用し、心身の回復に努めます。
- 働ける状態になったら失業手当に切り替える:主治医から「そろそろ求職活動を始めても良いでしょう」という許可が出たら、傷病手当金の受給を終了し、ハローワークで失業手当の受給手続き(または延長していた場合は受給開始の手続き)を行います。
このように、二つの制度をスムーズにバトンタッチさせることで、切れ目なく経済的な支援を受けながら、ご自身のペースで回復と社会復帰を目指すことができます。
【長期的な療養が必要な方】障害年金という、もう一つの大きな支え
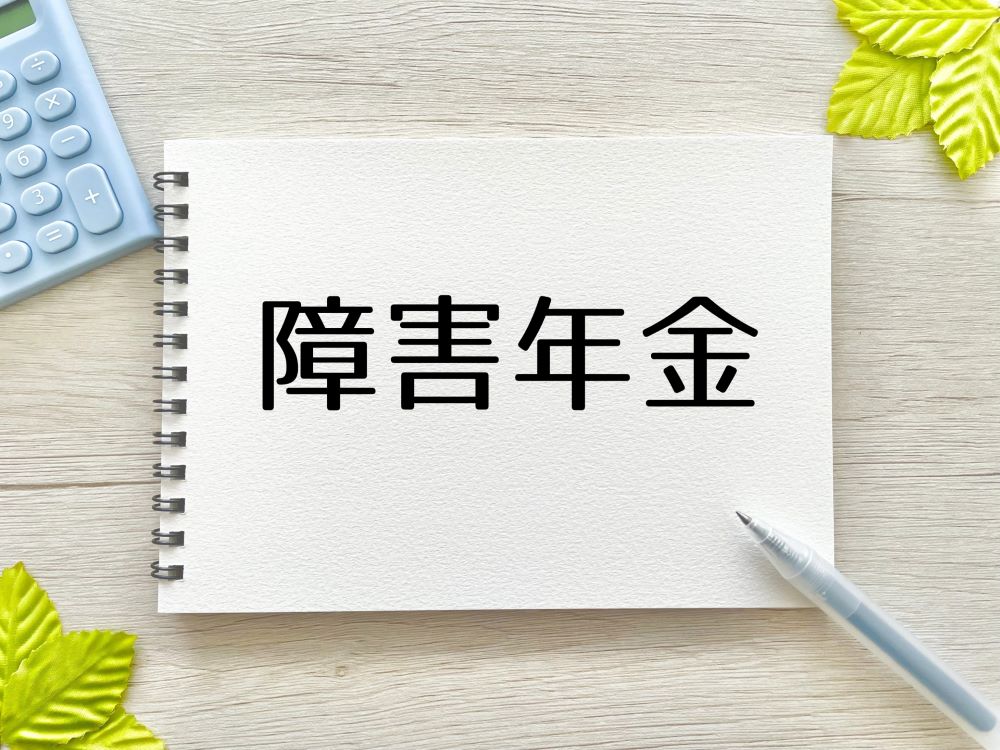
ここからは、当事務所の専門分野である「障害年金」について、特に詳しくお話しします。
傷病手当金や失業手当が、比較的短期的な生活の支えであるのに対し、障害年金は、うつ病による長期的な療養が必要な方の生活を、根本から支えることができる非常に重要な制度です。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事に著しい制限を受けるようになった場合に、現役世代の方でも受け取ることができる公的な年金制度です。
これは特別な人だけがもらえるものではなく、きちんと年金保険料を納めてきた方が受けられる正当な権利です。
うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患も、もちろん対象となります。
障害年金には、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって、2つの種類があります。
- 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、学生、会社員の配偶者など)が対象です。また、20歳前に初診日がある方もこちらに該当します。
- 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象です。障害の程度が1級または2級に該当する場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。また、障害厚生年金には、より軽度な3級や、一時金である障害手当金という制度もあります。
受給のための3つの重要要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべてクリアする必要があります。
この3つは、障害年金の申請における非常に重要なポイントです。
初診日要件
障害の原因となったうつ病で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた「初診日」が、年金の加入期間中(国民年金または厚生年金)にあることが必要です。
この初診日を証明できなければ、残念ながら申請手続きを進めることができません。
申請の第一歩は、この初診日を特定し、証明することから始まります。
保険料納付要件
初診日の前日時点で、年金保険料を一定期間以上、きちんと納めている必要があります。
具体的には、以下のいずれかを満たせばOKです。
- (原則) 初診日の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されていること。
- (特例) 初診日が65歳未満であり、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
「免除」の期間も納付した期間として扱われますので、過去に免除申請をしていた方もご安心ください。
障害状態該当要件
障害の程度が、法律で定められた障害等級(1級・2級・3級)に該当することが必要です。
この障害の程度を判断する基準となる日を「障害認定日」といい、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日とされています。
この障害認定日の時点で、一定の障害状態にあることが認められると、障害年金が支給されます。
うつ病における障害年金認定のポイント
うつ病などの精神疾患の場合、外見からは障害の程度が分かりにくいため、審査では「その症状によって、日常生活や働くことにどれだけの支障が出ているか」が最も重視されます。
その判断のために、特に重要となるのが「診断書」と、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」の2つの書類です。
① 診断書:最も重要な客観的証拠
審査において最も重視されるのが、主治医が作成する「診断書」です。
特に、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という項目が、等級を決定する上で大きな影響を持ちます。
- 日常生活能力の判定:「適切な食事」「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」など7つの項目について、どの程度できるかを医師が4段階で評価します。
- 日常生活能力の程度:「社会生活は普通にできる」から「身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要」まで、日常生活全般の支障の度合いを医師が5段階で評価します。
これらの評価が実態に即した適切なものになるよう、日頃の診察の際に、ご自身の日常生活での困難さ(例えば、「お風呂に週に1回しか入れない」「一人で買い物ができず、家族に頼んでいる」「集中力が続かず、簡単な調理もできない」など)を、具体的に、そして正直に主治医に伝えておくことが非常に大切です。
② 病歴・就労状況等申立書:あなたの声を届ける唯一の書類
診断書が医師による客観的な評価であるのに対し、「病歴・就労状況等申立書」は、ご自身の言葉で、発病から現在までの経緯や、日常生活・就労における困難さを審査官に直接伝えることができる、唯一無二の重要な書類です。
専門家として、作成のポイントをいくつかお伝えします。
- 診断書との整合性を保つ:申立書の内容と、診断書や初診日の証明書の内容に矛盾があると、書類全体の信憑性が疑われてしまいます。必ず提出前にすべての書類を見比べて、一貫性があるかを確認してください。
- 客観的・具体的に書く:「つらい」「苦しい」といった感情的な表現だけでは、困難さは伝わりません。「何が、どのようにできないのか」を、具体的なエピソードや数字を交えて客観的に記述しましょう。
- (悪い例)「気分が落ち込んで大変です。」
- (良い例)「意欲が湧かず、1日中ベッドから出られない日が週に3日あります。食事も1日1食がやっとで、入浴は週に1回が限界です。」
- 就労状況を詳しく書く:もし働いている場合でも、諦める必要はありません。「どのような配慮や援助を受けて、やっと働けているのか」を具体的に書くことが重要です。
- (例)「周りの方に業務を頻繁に手伝ってもらっている」「休憩を他の人より多く取らせてもらっている」「ミスが増え、簡単な作業に配置転換してもらった」など。
- 空白期間を作らない:発病から現在までの時系列を、途切れることなく記述します。病院に行っていなかった期間についても、「なぜ行かなかったのか」「その間、どのような症状で、どう生活していたのか」を必ず記入してください。
- 読みやすさを意識する:審査官が読みやすいように、丁寧な字で、可能であればパソコンで作成し、要点をまとめて簡潔に書くことを心がけましょう。ご家族など第三者に読んでもらい、分かりにくい部分がないかチェックしてもらうのも有効です。
申請から受給までの流れと期間
障害年金の申請は、一般的に以下の流れで進みます。
- 年金事務所での相談・初診日の確認
- 必要書類の準備
- 年金請求書
- 受診状況等証明書(初診の病院で取得)
- 医師の診断書(現在の主治医に依頼)
- 病歴・就労状況等申立書(本人または代理人が作成)
- 通帳や障害者手帳のコピーなど
- 年金事務所へ書類を提出
- 日本年金機構での審査
- 結果の通知・支給決定
申請書類を提出してから結果が出るまでには、一般的に3ヶ月から6ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。
書類の準備にも1〜2ヶ月かかることが多いため、長期戦になることを覚悟し、計画的に進めることが大切です。
手続きが複雑で難しいと感じる場合は、私たちのような障害年金専門の社会保険労務士に相談することも有効な選択肢の一つです。
収入確保と負担軽減のために使える制度
ここまで、収入を確保するための主要な3つの制度(傷病手当金、失業手当、障害年金)を詳しく見てきました。
しかし、あなたを支える制度はこれだけではありません。
医療費や税金の負担を軽くする制度、そして最後のセーフティネットとなる制度も存在します。
ここでは、これまで紹介した制度も含め、利用できる公的支援を一覧表にまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせながら、活用できるものがないかチェックしてみてください。
表3: うつ病で使える公的支援制度 比較表
| 制度名 | どんな制度? | 対象者(主な例) | もらえる内容・受けられる支援 | 相談・申請窓口 | ここがポイント |
| 傷病手当金 | 業務外の病気やケガで休職した際の所得保障 | 健康保険に加入する会社員・公務員 | 給与のおおむね2/3を最長で通算1年6ヶ月 | 会社の健康保険組合、協会けんぽ | 退職前に申請を開始することが、退職後も継続して受給するための鍵! |
| 失業手当 (雇用保険) | 失業中の生活を支え、再就職を促進する給付 | 離職し、働く意思と能力がある方 | 前職給与の5〜8割を90日〜360日 | ハローワーク | うつ病が理由なら「特定理由離職者」等に認定され、給付が有利になる可能性大。 |
| 障害年金 | 病気やケガで生活や仕事が制限される場合の年金 | 現役世代を含む年金加入者 | 障害等級に応じた年金(障害厚生年金は月平均10万円程度) | 年金事務所、市区町村役場 | 長期的な生活の基盤となる重要な制度。申請準備が複雑なため専門家への相談も有効。 |
| 労災保険 | 業務が原因の病気やケガに対する補償 | すべての労働者 | 療養費、休業補償など | 労働基準監督署 | うつ病の原因が長時間労働やハラスメントの場合に検討。 |
| 自立支援医療制度 | 精神疾患の医療費の自己負担を軽減する制度 | 精神疾患で通院治療を継続している方 | 医療費の自己負担が通常3割→原則1割に軽減(所得に応じた上限あり) | 市区町村の障害福祉担当窓口 | 通院が長期にわたる場合に必須の制度。必ず申請しましょう。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害の状態にあることを証明する手帳 | 精神疾患により長期にわたり生活に支障がある方 | 税金の控除(所得税・住民税)、公共料金の割引など | 市区町村の障害福祉担当窓口 | 障害年金と同時に申請できる場合も。税負担の軽減効果が大きい。 |
| 生活保護 | 生活に困窮する方への最後のセーフティネット | 資産や能力、他の制度を活用しても生活できない世帯 | 最低生活費から収入を引いた差額を支給。医療費は自己負担なし | 福祉事務所 | 国民の権利。持ち家や車があっても利用できる場合あり。ためらわずに相談を。 |
| 生活福祉資金貸付制度 | 低所得世帯などへの貸付制4 | 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯 | 生活再建のための資金などを無利子または低利子で貸付 | 市区町村の社会福祉協議会 | あくまで「貸付」だが、緊急時に生活をつなぐための選択肢。 |
医療費の負担を軽くする制度
うつ病の治療は、定期的な通院や服薬が必要となり、長期化することも少なくありません。
医療費の負担は想像以上に重くのしかかります。
その負担を大幅に軽減できる制度があります。
自立支援医療(精神通院医療)
これは、うつ病などの精神疾患で通院による治療を続ける必要がある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。
通常、医療費の自己負担は3割ですが、この制度を利用すると原則1割にまで軽減されます。
さらに、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設けられるため、それ以上の負担は発生しません。
申請はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。
継続的な通院が必要な方にとっては、利用すべき制度です。
税金の負担を軽くする制度
精神障害者保健福祉手帳
これは、一定程度の精神障害の状態にあることを証明するための手帳です。
この手帳の交付を受けると、障害の等級に応じて、所得税や住民税の「障害者控除」が適用され、税金の負担が軽くなります。
また、自治体によっては公共交通機関や公共施設の料金割引などのサービスを受けられる場合もあります。
障害年金を申請する際に、同時に申請手続きができることも多いので、市区町村の窓口で確認してみましょう。
どうしても生活が困難な時の最終的なセーフティネット
あらゆる制度を使っても、どうしても生活が立ち行かない。
そんな時のために、国には最後のセーフティネットが用意されています。
生活保護
生活保護は、資産や働く能力、他のあらゆる制度を活用してもなお生活に困窮する方に対し、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を助けるための制度です。
「親族に迷惑がかかる」「持ち家や車があると申請できない」といった誤解から、利用をためらう方が少なくありません。
しかし、扶養はあくまで義務ではなく協力のお願いであり、連絡を拒否することも可能です。
また、居住用の持ち家や、通勤・通院に必要な車などの保有が認められるケースもあります。
生活保護は、困窮から抜け出すための国民の権利です。一人で抱え込まず、まずはお住まいの地域を管轄する福祉事務所に相談してください。
生活福祉資金貸付制度
これは、低所得世帯や障害者世帯などを対象に、社会福祉協議会が窓口となって、生活再建に必要な資金を無利子または低利子で貸し付ける制度です。
あくまで「貸付」なので返済が必要ですが、公的な融資が受けられない場合の緊急的なつなぎ資金として、知っておくと心強い制度です。
社会復帰に向けたサポート
療養が進み、少しずつ「また働きたい」という気持ちが芽生えてきたとき、焦りは禁物です。
うつ病は再発しやすい病気でもあり、スムーズな社会復帰のためには専門的なサポートの活用が非常に有効です。
あなたの状況に合わせて、主に2つの支援プログラムがあります。
リワーク支援
現在休職中で、元の職場への復帰を目指す方のためのプログラムです。
医療機関や地域障害者職業センター、福祉サービス事業所などで実施されており、生活リズムの改善、体力回復、ストレス対処法の習得、模擬的なオフィスワークなどを通じて、再発を防ぎながら円滑な職場復帰をサポートします。
就労移行支援
会社を退職し、新しい職場への就職を目指す方のための福祉サービスです。
就労移行支援事業所に通いながら、職業訓練、自己分析、ビジネスマナー、就職活動のサポート、そして就職後の定着支援まで、一貫したサポートを受けることができます。
うつ病の特性に配慮したプログラムを提供している事業所も多くあります。
どちらの支援も、あなたと同じような悩みを持つ仲間と出会える場でもあります。
一人で抱え込まず、こうした支援機関に相談してみることも、社会復帰への大きな一歩となるでしょう。
まとめ

ここまで、うつ病で働けなくなった時に利用できる、様々な公的支援制度について解説してきました。
多くの制度があり、手続きも複雑で、圧倒されてしまったかもしれません。
しかし、一番お伝えしたいのは、「これだけ多くのセーフティネットが、あなたのために用意されている」ということです。
今の状況は、決してあなたのせいではありません。
うつ病は、誰にでも起こりうる病気です。
そして、その治療で最も大切なのは、お金の心配をせず、安心して心と体を休めることです。
この記事を読んで、「自分にも使える制度があるかもしれない」と少しでも感じていただけたなら、まずは小さな一歩を踏み出してみてください。
主治医に相談する。
お住まいの市区町村役場や福祉事務所、年金事務所に電話を一本入れてみる。
それだけで、道は拓けていきます。
もし、手続きが難しくて一人では無理だと感じたら、どうか私たちのような社会保険労務士や、弁護士といった専門家の存在を思い出してください。
私たちは、複雑な制度の迷路を抜け出すための伴走者です。
あなたは、決して一人ではありません。
どうかご自身を責めず、頼れるものを頼り、今はご自身の回復だけに専念してください。
この記事が、あなたの心の重荷を少しでも軽くし、未来への希望を灯すきっかけとなったなら、専門家としてこれ以上の喜びはありません。
わくわく社労士法人が選ばれる理由
2025年11月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が602件、Googleに投稿頂いたクチコミが260件あります。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)
【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
(匿名様からのご感想)

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
(匿名様からのご感想)
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら
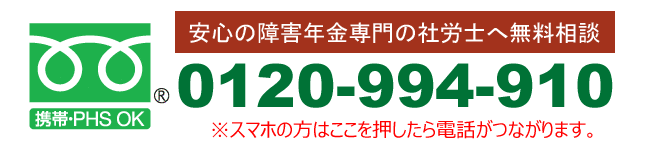
LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。