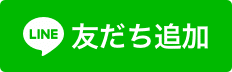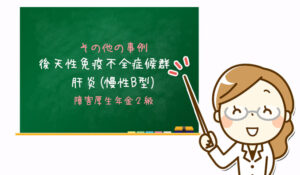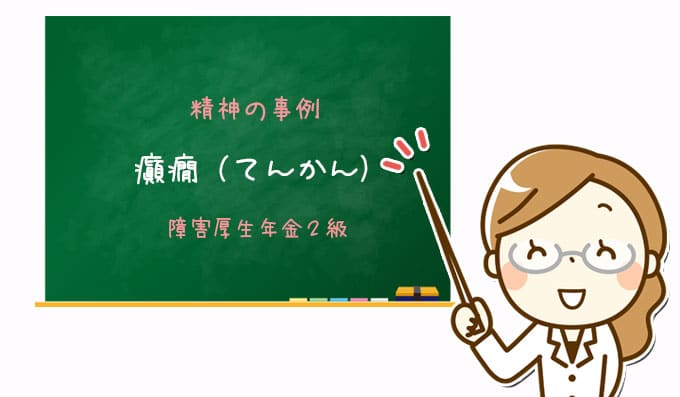
目次
対象者の基本データ
| 病名 | 癲癇(てんかん) |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 支給額 | 年額 約177万円 |
| 障害の状態 |
|
| 申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
今回ご相談いただいたのは、てんかんを抱えるご依頼者様の配偶者様でした。
ご本人との直接のやり取りが難しい中、認定日と現在の2通の診断書を取得された段階で「自分たちだけでは進めるのが難しい」と当社へサポートのご依頼をいただきました。
取得されていた診断書を拝見したところ、初診日の記載がされていない。発病日が相違しており、それぞれの診断書に整合性がない。
さらには「現在の診断書に申請傷病であるてんかんの症状記載がない」といった、いくつもの課題が見つかりました。
準備されていた書類とご依頼者様からのヒアリングをもとに申請方針をイチから検討して申請書類を整備していくこととなりました。
申請のポイント
①複数傷病の初診日証明
ご依頼者様の病歴を整理すると、まず初診日の特定が難しいケースでした。
ご依頼者様は過去に髄膜炎(平成4年)を発症しており、その後てんかん(平成19年)を発病されています。
髄膜炎によってもけいれん発作を認めるケースが有る為、今回の申請傷病であるてんかんとは切り分けて、てんかんの初診日を明確にする必要があると考えました。
そのため、申請傷病はてんかんでしたが、病歴就労状況等申立書には平成4年からの髄膜炎の経過についても記載を行い、仮にてんかんとの関連性があるとされても、てんかん発病までの期間に社会的治癒期間があることを補足で申立ても行うこととしました。
②複数傷病での診断書
初診日が確定した段階で診断書の取得へと進めていきます。
当初ご依頼者様が準備されていた診断書では「髄膜炎」「高次脳機能障害」「てんかん」と3つの傷病が記載されていたため、てんかん単独での状態が読み取りにくい状況で、また初診日もてんかんでの初診日ではない記載がされていた為、障害認定日も異なる日付で診断書を取得されていました。
このままの内容では適切な審査を受けることができない為、診断書は再度イチから作成していただくことにしました。
再取得にあたっては、「てんかん」にて申請を行う旨を明確にお伝えし、てんかんの初診日に関する資料を添付し、てんかんの自覚症状・日常生活状況などを参考資料としてまとめ、橋渡しを行いました。
現状として3つの傷病を併発していることは事実である為、再取得した診断書も同様に3傷病の記載がありましたが、「てんかん部分のみを抽出」して見たところ、てんかんによって日常生活や仕事への支障が大きいことが確認できる内容となっていました。
当初ご依頼者様が準備されていた初診日とは異なる初診日にて申請を行うこととなった為、障害認定日も大きく異なる事となり、障害認定日から3か月以内の受診歴がなく、原則の認定日診断書取得はできませんでしたが、取得可能な限り認定日に近い日付で診断書を作成していただき、認定日請求にチャレンジしました。
結果
申請の結果、障害認定日は不支給となりましたが、事後重症は2級として認定されました。
複数傷病が併存している為、初診日・障害状態ともにどのように審査されるか懸念されましたが、方針立ての通り、それぞれの傷病に相当因果関係はないという認定医の判断もあり、てんかん単独の経過・症状に着目された上で申立ての通りに認定となりました。
スタッフの感想
今回の事例では3つの傷病があったため、初診日の証明・障害の状態の証明にかかる診断書、病歴就労状況等申立書の整備全てにおいて、難易度が高いケースでした。
しかし、代理人の配偶者様からの情報提供と各医療機関様のご理解ご協力もあり、1つずつステップを踏むことで方針立ての通りに書類整備を進める事ができました。
複数の傷病がある場合、それぞれの傷病が複雑に交わり、日常生活への影響も大きくなる傾向にあると思われます。
また異なる傷病でも類似した症状が出ている場合は通院歴についても複雑になるケースは少なくないと思います。
そのため、複数傷病がある場合は障害年金の手続きが煩雑になり、通常よりも時間を要する可能性があります。
そんな時でも1つずつ紐解き、順を追って申請までのステップを踏んでいくことが結果的に一番の近道になります。
不要な書類の取得を避けるためにもご自身でお手続きを進めていただく際は年金事務所の窓口にてご相談していただくことより、手続きをスタートされることをオススメ致します。
また、複数傷病でどのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。
【ポイント1】複数傷病がある場合の初診日
障害年金では原則としてて『傷病ごとに初診日を確定』させる必要があります。
それぞれ同じ病院に通院している場合であっても『それぞれの病気の初診日』を確定させましょう。
単に病院の初診日を確認するだけでは、いずれの病気に対する初診日は不明確ですので、必ず病気ごとの初診日を確認するようにしましょう。
【ポイント2】てんかんの注意点
てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を利用します。
その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。
①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定
病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。
例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。
その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと「発作はあるけど生活には問題がないんだね」と不支給とされるケースがあるのです。
それを防ぐためにも、発作の無い期間であっても、いつ発作が起きるか分からない事から、どのような影響があるのかを、しっかりとわかるように申請を行う事が大切となります。
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら
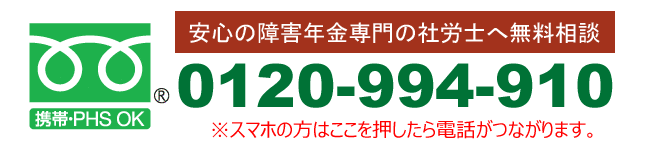
LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。