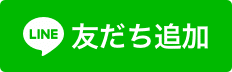目次
対象者の基本データ
| 病名 | 双極性感情障害 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 支給額 | 年額 約61万円 |
| 障害の状態 | ・休職中で就労できない状態である。 ・コミュニケーション能力が低下しており家族との会話も限定的である。 ・家事や保清など基本的な身の回りのことにも家族の支援が必要。 ・判断能力も低下しており金銭管理や服薬管理も家族任せとなっている。 |
| 申請結果 | 障害厚生年金3級 |
本事例の内容は以下の動画でも説明していますので、是非あわせてご視聴ください。
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
今回のご依頼者様は、躁うつ性障害(双極性障害)を抱えながらも、一般企業に27年以上勤続されていた女性の方でした。
令和5年11月に現症日の診断書を取得され、同年12月に障害年金の申請をされましたが、残念ながら令和6年5月に「不支給」の通知を受け取られました。
当社としても申請書・診断書に「職場の配慮」や「日常生活の困難さ」を丁寧に記載し、就労の実態を説明したつもりでした。
不支給の理由を明確に確認するため認定調書を取得したところ、「就労は継続できている」「昇給している」といった“外形的な要素”が重視され、非該当との判断となった事がわかりました。
その後、症状が悪化し再度、申請のやり直しについて弊社にご相談頂くこととなりました。
申請のポイントと課題
審査請求も検討しましたが、ご依頼者様はちょうど不支給決定の直前、令和6年4月から「休職」に入っておられました。
さらに、その後の令和6年7月末から8月中旬にかけては入院も経験されています。
この状況の変化を踏まえ、私たちは「一から申請をやり直す」判断をしました。
ポイントとなったのは、「休職」していたという事実と、その状態を反映した新たな診断書の取得です。
令和6年7月24日付の診断書では、就労していない状態が明記されており、日常生活の状況についても正確に反映されており3級相当と判断できるものでした。
申請は令和6年8月27日に行い、審査も予想以上にスムーズに行われ、約2ヶ月後の10月17日には「障害厚生年金3級」の認定が出ました。
結果と対応の工夫
今回のケースでは、1回目の申請で不支給となったにもかかわらず、「就労を休んでいる」ことをしっかり示すことで再申請が認められた形です。
前回の結果後に取寄せた認定調書では、簡潔に「休職中」とだけ記載されており、就労継続の有無が大きく判断に影響していたことがわかります。
また、初回の認定時に「昇給している」と明記されていた点からも、年金機構が「就労の有無」だけでなく「給与の内容や昇給の有無」にも着目していることが読み取れました。
昇給されていても、その昇給が能力の評価ではなく社員全員が一律に賃金が上がる「定期昇給」であれば、会社から昇給の規定などを取寄せて申請することが有効な手段になると考えられます。
スタッフの感想と今後への学び
今回の再申請は、前回からの期間が短いながらも、明確な生活状況の変化(休職・入院)を示せたことがポイントでした。
一度、不支給になっても諦めずに申請をやり直すことで受給に結びつくということを再確認できました。
スタッフ間でも「外形的な事実(就労の有無・給与の変化)」が、実際の申請結果に大きく影響していることが再確認されました。
「仕事をしている」だけでなく、「どのように働いているか」「職場からどんな配慮を受けているか」「給与の上がり方の理由」など、より細かな情報の積み重ねが、正確な等級認定につながると感じました。
本事例のポイントとFAQ
【ポイント1】躁状態に注意
双極性障害は「鬱状態と躁状態を繰り返すこと」を特徴としており、躁状態では元気と捉えられてしまう可能性もあります。
医師は診察時の状況しか診ることができないため、家庭内で「躁状態と思われる行動」がある場合、診察時に医師に伝えることが大切です。
【ポイント2】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント3】個人情報の開示請求
障害年金を申請して不支給になった場合や支給決定を得られたものの納得のいく等級が得られなかった場合に、再度一から裁定請求や審査請求を検討していくこととなります。
決定内容には何らかの理由があって決定がなされていますので、「なぜそのような決定になったのか」その理由を知り、再度の裁定請求や審査請求に臨むことが大切です。
その理由を知る方法の一つに「個人情報開示請求」を行い、認定調書の写しを入手する方法があります。
個人情報の開示請求は厚生労働大臣宛てで行います。
手続きの方法や流れは下記URLをご参照ください。
本事例に関するよくあるご質問
Q1: 双極性感情障害で障害年金を申請する際の主な注意点は何ですか?
A1: 双極性感情障害の場合、躁状態と鬱状態を繰り返す特性があるため、特に躁状態が「元気な状態」と誤解されやすい点に注意が必要です。
診察時に医師は限られた時間しか診ることができないため、家庭内で見られる「躁状態と思われる行動」を具体的に医師に伝えることが非常に重要です。
これにより、診断書に病状が正確に反映され、適切な等級認定につながる可能性が高まります。
Q2: 障害年金の審査において「就労の有無」はどのように影響しますか?
A2: 精神疾患の場合、就労の有無は審査において重要なポイントとなります。
必ずしも「就労している=不支給」とは限りませんが、継続年数や就労形態も審査で見られます。
就労している場合でも、職場からの配慮の内容(例:早退、遅刻、業務内容の調整など)や、帰宅後や休日の体調(例:帰宅後すぐに寝込んでしまう、休日は家事ができないなど)を具体的に申し立て、診断書に反映させることが必要です。
単に「仕事をしている」だけでなく、「どのように働いているか」を詳細に伝えることが重要です。
Q3: 不支給になった後、再申請する際のポイントは何ですか?
A3: 一度不支給になっても諦めずに再申請することで受給につながる可能性があります。
再申請のポイントは、前回の不支給理由を把握し、症状や生活状況の変化を明確に示すことです。
特に、不支給後に休職や入院といった状況の変化があった場合は、それを反映した新たな診断書を取得し、現在の就労状況や日常生活の困難さをより具体的に示すことが有効です。
今回の事例でも、休職と入院という明確な変化を示すことで、短期間での再認定につながりました。
Q4: 障害年金の審査では「給与の内容や昇給の有無」も考慮されますか?
A4: はい、障害年金の審査では、就労の有無だけでなく、給与の内容や昇給の有無も判断材料として考慮されることがあります。
事例では、前回の申請時に「昇給している」ことが不支給の理由の一つと判断されました。
もし昇給が能力評価によるものではなく、社員全員が一律に賃金が上がる「定期昇給」である場合は、会社の昇給規定などを取り寄せ、その旨を説明することが有効な手段となり得ます。
給与が高い、または昇給していると「きちんと仕事ができている」と判断されやすいため、その実態を正確に伝える工夫が必要です。
Q5: 不支給になった理由を知るにはどうすればよいですか?
A5: 障害年金の申請で不支給になった場合、その決定理由を知ることは再申請や審査請求を行う上で非常に重要です。
理由を知る方法の一つに「個人情報開示請求」を行い、認定調書の写しを入手する方法があります。
これは厚生労働大臣宛てに行う手続きです。認定調書には、年金機構がどのような判断基準で決定を下したのかが記載されており、これにより次回の申請で不足していた点や誤解された点を特定し、対策を講じることができます。
Q6: 短期間の休職や入院でも障害年金の認定に影響しますか?
A6: 短期間の休職や入院であっても、それが診断書に明確に反映され、就労や日常生活への影響を示していれば、認定に大きく影響する可能性があります。
今回の事例では、不支給通知の直前に休職に入り、その後入院したという状況の変化が、再申請で3級認定につながりました。
心配される長期の休職期間がなくても、症状の悪化や就労困難な状況が客観的に示されることが重要です。
Q7: 障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?
A7: 障害年金は申請書類が多く複雑なため、社会保険労務士に依頼することで、専門的な知識に基づいたサポートを受けられます。
特に、診断書の内容や申立書の作成において、病状や日常生活の困難さ、就労実態(職場からの配慮や給与の性質など)を正確かつ具体的に伝えるためのアドバイスを得られます。
今回の事例のように一度不支給になったケースでも、不支給理由を分析し、状況変化に応じた再申請の戦略を立てるなど、認定に向けたきめ細やかなサポートが期待できます。
電話やLINEでの無料相談に対応している事務所もあり、気軽に相談できる体制が整っています。
Q8: 診断書作成時に医師に伝えるべき重要なポイントは何ですか?
A8: 診断書は障害年金申請の最も重要な書類の一つです。診察時だけでなく、日常生活での困難さや就労における具体的な支障、家族からの支援状況などを医師に正確に伝えることが不可欠です。
例えば、家事や身の回りのことへの支援の必要性、金銭管理や服薬管理の状況、コミュニケーション能力の低下などが挙げられます。
また、仕事をしている場合でも、会社での配慮内容や、帰宅後・休日の体調悪化なども詳細に伝えることで、診断書に病状がより正確に反映され、認定に有利に働く可能性があります。
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら
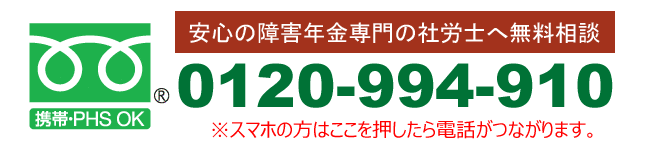
LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。