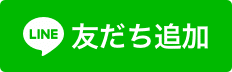「障害年金は、いったいいつから受け取れるのだろう?」
この記事をご覧になっている方の中には、そんな疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
病気やケガでつらい思いをされている中で、生活の支えとなる年金がいつ手元に届くのかは、何よりも気になりますよね。
実は、障害年金の「いつから」という疑問には、2つの異なる意味が含まれています。
- 受給権発生月: 法律上、年金を受け取る「権利」が始まる月
- 初回振込日: 実際にあなたの銀行口座に、初めてお金が「振り込まれる」日
この2つの違いを理解することが、不安を解消し、今後の生活設計を立てるための第一歩です。
多くの方が、権利が発生してから実際にお金を受け取るまでに数ヶ月の期間が空くことを知らず、戸惑ってしまいます。
この期間は、申請の準備から審査、支払い手続きを含めると、全体で半年以上かかることも珍しくありません。
この記事では、この「権利が始まる月」と「実際に振り込まれる日」の両方について、分かりやすく解説していきたいと思います。
目次
【いつからもらえる1】障害年金の受給開始月はいつ?

まず最初に、法律上の「受給権」がいつから発生するのかを見ていきましょう。
これは、あなたがどの方法で障害年金を請求するかによって決まります。
請求方法には、大きく分けて3つのパターンがあります。
【パターン1】認定日請求(本来請求)
「認定日請求」とは、障害の状態を判断する基準日である「障害認定日」時点の障害の程度に基づいて年金を請求する方法です。
障害認定日から1年以内に請求を行う場合が、このパターンに該当します。
「障害認定日」とは?
障害認定日とは、あなたの障害の状態を国が認定するための基準日です。
原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月が経過した日を指します。
例えば、初診日が2023年4月10日だった場合、原則的な障害認定日は2024年10月10日となります。
ただし、これにはいくつかの例外があります。
- 症状が固定した場合: 1年6ヶ月経つ前に症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態になった場合は、その症状が固定した日が障害認定日となります。
- 20歳前に初診日がある場合: 初診日が20歳より前にある場合、障害認定日は「初診日から1年6ヶ月経った日」または「20歳の誕生日(の前日)」のいずれか遅い方の日となります。
受給開始月
認定日請求が認められた場合、年金は障害認定日の翌月分から支給が開始されます。
例えば、障害認定日が2024年10月10日であれば、2024年11月分から年金を受け取る権利が発生します。
【重要】1年6ヶ月を待たずに請求できる特例ケース
多くの方が「初診日から1年6ヶ月は必ず待たなければならない」と思われていますが、実はそうではありません。
特定の医療的処置を受けたり、特定の症状になったりした場合は、1年6ヶ月を待たずに、その日が障害認定日となる「特例」が法律で定められています。
この特例を知っているかどうかで、年金の受給開始が1年以上早まる可能性もあります。
ご自身の状況が当てはまらないか、ぜひ下の表で確認してみてください。
表1:1年6ヶ月を待たずに請求できる特例ケースの例
| 状態・処置 | 障害認定日となる日 |
| 人工骨頭・人工関節の挿入置換 | 挿入置換した日 |
| 心臓ペースメーカー・ICDの装着 | 装着した日 |
| 人工心臓弁の置換 | 装着した日 |
| 人工肛門・新膀胱の造設 | 造設日から6ヶ月を経過した日 |
| 咽頭(のど)の全摘出 | 全摘出した日 |
| 肢体の切断・離断 | 原則として切断・離断した日 |
| 在宅酸素療法の開始 | 開始した日 |
| 脳血管障害による機能障害 | 初診日から6ヶ月経過後、症状が固定したと認められた日 |
例えば、初診日から3ヶ月後に人工関節を入れた場合、1年6ヶ月を待つ必要はなく、手術日が障害認定日となります。
これにより、本来よりも15ヶ月も早く年金を受け取り始めることができます。
【パターン2】遡及請求
これは、障害認定日の時点では障害等級に該当する状態だったにもかかわらず、当時は制度を知らなかった、あるいは体調が悪くて手続きができなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過してから請求するパターンです。
受給開始月
遡及請求が認められた場合、受給権の発生はパターン1と同じく、本来の障害認定日の翌月分からとなります。
ただし、遡及請求の場合は重要なポイントがあります。
年金を受け取る権利には5年の「時効」があります。
たとえ10年前に受給権が発生していたとしても、実際にさかのぼって受け取れるのは、請求した日から最大で過去5年分に限られます。
例えば、以下の場合を考えてみましょう。
- 障害認定日:8年前の2016年5月
- 請求日:2024年5月
この場合、年金を受け取る権利は2016年6月分から発生しますが、時効により2016年6月分~2019年3月分は消滅してしまいます。
実際に受け取れるのは、時効にかからない過去5年分、つまり2019年4月分から請求月までの分となります。
また、遡及請求は過去の事実を証明する、「証拠集め」の作業が必要になります。
成功の鍵は、障害認定日当時の状態を証明する診断書やカルテを用意できるかにかかっています。
しかし、医療機関でのカルテの法定保存期間は5年と定められているため、5年以上前の記録は破棄されている可能性があります。
このため、遡及請求は証拠集めが難しく、専門家のサポートが特に有効なケースと言えます。
【パターン3】事後重症請求
これは、障害認定日の時点では症状が軽く、障害等級には該当しなかったものの、その後、症状が悪化して障害等級に該当する状態になった場合に用いる請求方法です。
障害認定日当時のカルテがなく遡及請求ができない場合の受け皿にもなります。
受給開始月
事後重症請求の場合、年金は請求した月の翌月分から支給が開始されます。
<注意点> 1日の遅れが1ヶ月分の損失に
事後重症請求では、過去にさかのぼって年金を受け取ることは一切できません。
受給開始は、完全に「請求日」に依存します。
これがどれほど重要か、具体例で見てみましょう。
- 1月31日に請求した場合: 支給開始は2月分から
- 2月1日に請求した場合: 支給開始は3月分から
たった1日、請求が遅れただけで、1ヶ月分の年金を永久に失ってしまうのです。
事後重症請求に該当する可能性のある方は、とにかく1日でも早く請求手続きを開始することが、ご自身の経済的な利益を守る上で非常に重要です。
なお、この請求は原則として65歳になる誕生日の前々日までに請求する必要があります 9。
3つの請求パターン比較表
ここまで解説した3つのパターンの違いを、一覧表にまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせて、最終確認をしてみてください。
| 請求方法 | 受給開始月 | 過去分の受給 | 必要な診断書 | 最大の注意点 |
| 認定日請求(本来請求) | 障害認定日の翌月 | 〇 | 障害認定日より3カ月以内の現症の診断書 | 認定日から1年以内に請求する |
| 遡及請求 | 障害認定日の翌月 | 〇 (最大5年分) | 障害認定日より3カ月以内の現症の診断書と直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)2枚 | 5年の時効と証拠集めが最大の壁 |
| 事後重症請求 | 請求した月の翌月 | × | 直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの) | とにかく1日でも早く請求する |
【いつからもらえる2】障害年金が初めて振り込まれる日はいつ?

今までの説明で、あなたの「受給権が始まる月」がわかったと思います。
ここからは、もう一つの「いつから」、つまり「実際に銀行口座にお金が振り込まれる日」までの流れを具体的に見ていきましょう。
申請から初回振込までの流れ
まずは全体の流れをつかみましょう。
[書類提出] → [審査期間:約3~5ヶ月] → [年金証書が届く] → [支払処理期間:約50日] → [初回振込]
このように、申請書類を提出してから実際に最初の振込があるまでには、合計で4ヶ月半から半年程度の期間がかかるのが一般的な目安です。(※後述しますように、審査によってはさらに長くかかる場合もあります。)
書類提出から決定までの「審査期間」
提出された書類は、年金事務所での形式チェックの後、東京にある日本年金機構の「障害年金センター」に送られ、専門の審査官によって内容の審査が行われます。
この審査にかかる期間の目安は、約3ヶ月とされています。
ただし、これはあくまで目安であり、診断書の内容について医師に照会が必要な場合など、複雑なケースではさらに時間がかかることもあります。
審査の結果、支給が決定されると「年金証書」が、不支給の場合は「不支給決定通知書」や「却下決定通知」がご自宅に届きます。
年金証書が届いてから「初回振込」まで
無事に支給が決定し、「年金証書」が手元に届いても、すぐにお金が振り込まれるわけではありません。
ここから初回振込までには、おおむね50日(約1ヶ月半)程度の期間が必要です。
年金証書を見れば、初回振込日をかなり正確に予測することができます。
年金証書に記載されている「裁定日」という日付を確認してください。
これは、日本年金機構があなたの年金支給を決定した日です。
この裁定日の日付によって、初回振込日は以下のように予測できます。
- 裁定日が月の前半(おおむね15日まで)の場合 → 初回振込は翌月の15日
- 裁定日が月の後半(おおむね16日以降)の場合 → 初回振込は翌々月の15日
年金証書が3月20日に届き、記載されている「裁定日」が3月18日だったとします。
裁定日が月の後半なので、初回振込日は翌々月の5月15日になる可能性が高いと予測できます。
そして、振込日の1週間ほど前になると、最終的な振込日と金額が記載された「年金支払通知書」が届きます。
これで、正確な日付と金額が確定します。
初回に振り込まれる金額について
初回振込では、まとまった金額が一括で振り込まれます。
この金額は、あなたの「受給権発生月」から、振込月までの合計額です。
具体例(遡及請求の場合):
- 受給権発生月:2024年10月(11月分から支払対象)
- 初回振込日:2025年4月15日
この場合、初回の振込額は、2024年11月、12月、2025年1月、2月、3月の合計5ヶ月分が一括で支払われます。
2回目以降の振込日
初回の振込が終わった後の定期的な支払いは、決まったスケジュールで行われます。
- 振込日: 毎年、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日。
- 支払われる分: 振込月の前月と前々月の2ヶ月分が支払われます(例:4月15日の振込は、2月分と3月分)。
- 休日・祝日の場合: 15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
給与のように毎月振り込まれるわけではないので、計画的な家計管理を心がけましょう。
まとめ

障害年金が「いつからもらえるのか」という疑問について、2つの側面から詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 受給権が始まる月は3つの請求パターンで決まる
- 認定日請求・遡及請求: 「障害認定日」の翌月から。ただし遡及請求は最大5年分の支払い。
- 事後重症請求: 「請求した月」の翌月から。
- 申請から初回振込までは4ヶ月半~半年が目安
- 事後重症請求は、1日でも早く請求することが金銭的に最も有利
障害年金の請求手続きは、複雑で時間がかかり、精神的にも大きな負担となることと思います。
しかし、この制度は、病気やケガと向き合うあなたの生活を支えるための大切な権利です。
この記事で、あなたの「いつから?」という不安が少しでも和らぐ一助になりましたら幸いです。
過去にさかのぼる遡及請求や、ご自身の状況がどのパターンに当てはまるか判断が難しい場合は、一人で悩まずに、ぜひ私たちのような社会保険労務士にご相談ください。
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら
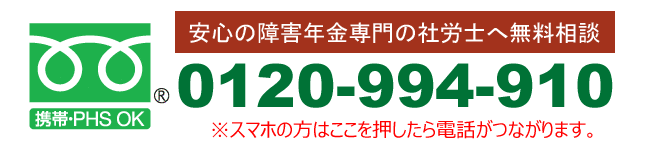
LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。