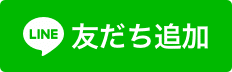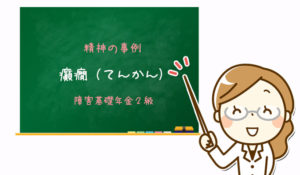目次
対象者の基本データ
| 病名 | 双極性感情障害 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 支給額 | 年額 約83万円 |
| 障害の状態 | ・躁状態においては、浪費が増え、家族に対しても攻撃性が高まる ・うつ状態においては1日中寝たきりで、食事や入浴もできない ・精神障害者保健福祉手帳2級 |
| 申請結果 | 障害基礎年金2級 |
本事例の内容は以下の動画でも説明していますので、是非あわせてご視聴ください。
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、双極性感情障害(躁うつ病)を患いながら、なんとか生活を維持してこられました。
病状には波があり、躁状態のときは過活動になってトラブルを招くことも多く、うつ状態のときには全く動けず、日常生活を送るのがやっとという状態が続いていました。
就労も週に1〜2回が限度で、職場ではご病気に配慮いただいていたものの、遅刻や欠勤が多く、安定して働くことが難しい状況でした。
療養期間が長期に渡っていることで今後の生活や治療の継続に強い不安を抱える中、障害年金の制度をインターネットで知り、「自分ももしかしたら対象になるのでは」と思い立ち、当社にご相談いただきました。
しかし、詳しくお話をうかがうと、初診が5年以上前であり、最初に受診したA病院ではすでにカルテが破棄されており、初診日を証明する書類が取得できないという、大きな壁が立ちはだかっていました。
それでも「できることはやってみたい」と当事務所にサポートのご相談を頂きました。
①申請のポイントと苦労した点
今回の事例でのポイントは、大きく分けて2つあります。
初診日の特定が困難だったこと
初診とされるA病院の受診記録が取れなかったため、B病院の証明書に基づき、A病院での受診時期は「平成25年9月頃」と推定することはできましたが、それ以上具体的な初診日を証明することの出来る書類取得はできませんでした。
具体的な日付までは特定できず、当該9月中は国民年金と厚生年金の異なる年金制度の加入期間が混在していたため、初診日の時点においていずれの年金制度に加入されているか明確にすることのできない状況下でしたが、9月中のいずれの日が初診日であっても保険料の納付要件を満たしていることから、「障害厚生年金」を主位的請求として、予備的に障害基礎年金の請求を行うこととしました。
申請後に年金機構から返戻があり、障害厚生年金での審査継続を希望する場合は厚生年金加入中の初診日を証明する資料の追加提出を求められました。
追加で提出できる資料がなかったため、最終的には予備的請求として準備していた「障害基礎年金」での申請に切り替えることとなりました。
診断書の等級がガイドライン上「目安外」だったこと
取得した診断書では日常生活能力の判定の平均が2.8、程度は(2)と記載されており、障害年金のガイドラインに照らすと、どの等級にも該当しないという「等級目安外」の状態でした。
また、就労に関しては職場では病状を理解してもらい配慮を受けながら週に1~2回勤務されていましたが、遅刻・早退・欠勤が多く、安定して働けない状況でした。
等級目安外の場合であっても、症状や日常生活・就労状況も踏まえた総合的な判断となるため、最後までどのような審査判断となるか見込みのつかない状況でした。
②結果
当初は等級の目安に該当しないことと障害基礎年金での申請となったことから不支給の可能性もあると考えていましたが、最終的には障害基礎年金2級が認められました。
認定に至った大きな要因は、申立書において「躁状態」と「うつ状態」それぞれの生活上の困難を丁寧に記載した点であると考えています。
躁のときには友人に連絡を取りすぎて予定を詰め込み、結果的にすべてをキャンセルしたり、暴言を吐いてしまうなど、一見活動的に見えるが実際には日常生活に著しい支障が出ている様子を具体的に説明しました。
うつ状態では何も手につかず、一日中寝たきりのような生活になることも多く、両方の状態をバランスよく申立てたことで、現実的な生活実態が伝わったのだと考えられます。
③スタッフの感想と強調すべきポイント
この事例から学べる最も重要なポイントは、「ガイドライン上で等級目安外でも、実際の生活状況を丁寧に伝えることで認定される可能性がある」ということです。
特に双極性感情障害のように症状の波が大きい疾患では、「活動的なとき(躁)」だけで判断されてしまうと、本当の困難が伝わりにくいという懸念があります。
そのため、診断書や申立書だけでなく、参考資料やヒアリングシートを活用し、「その活動は適切なのか」「周囲にどれだけの迷惑がかかっているか」などといった視点を忘れずに伝えることが大切であると再認識出来る事例でした。
本事例のポイントとFAQ
本事例のポイント
本事例のポイントを以下にご説明します。
【ポイント1】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』
障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。
①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』
- 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中、60歳以上65歳未満で制度未加入者等
- 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
- 加算:2級以上で子の加算
②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』
- 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
- 等級:1,2、3級のいずれかに該当
- 加算:2級以上で子・配偶者加算
③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』
- 対象:公務員等
- 等級:1,2、3級のいずれかに該当
- 加算:2級以上で子・配偶者加算
初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】躁状態に注意
双極性障害は「鬱状態と躁状態を繰り返すこと」を特徴としており、躁状態では元気と捉えられてしまう可能性もあります。
医師は診察時の状況しか診ることができないため、家庭内で「躁状態と思われる行動」がある場合、診察時に医師に伝えることが大切です。
本事例に関するよくあるご質問
本事例に関してよくいただく質問をご紹介します。
1. 双極性感情障害での障害年金申請において、初診日の特定が困難な場合でも受給は可能ですか?
はい、可能です。事例では、初診とされた病院のカルテが破棄されており、具体的な初診日を証明する書類の取得が困難でした。
この場合、他の病院の証明書からおおよその受診時期を推定し、初診日における年金制度の加入状況が不明確であっても、保険料納付要件を満たしていれば申請を進めることができます。
当初は障害厚生年金での申請を目指しつつも、最終的には障害基礎年金での申請に切り替え、認められたケースもあります。
2. 診断書の等級が障害年金のガイドラインで「目安外」と判断された場合、障害年金の受給は難しいのでしょうか?
いいえ、必ずしもそうではありません。ガイドライン上で「等級目安外」とされていても、実際の症状や日常生活、就労状況などを総合的に判断して認定される可能性があります。
特に双極性感情障害のように症状の波が大きい疾患では、診断書や申立書だけでなく、参考資料やヒアリングシートなどを活用し、躁状態と鬱状態それぞれの生活上の困難さを具体的に伝えることが重要です。
3. 双極性感情障害の「躁状態」は、障害年金の審査においてどのように評価されますか?
躁状態は一見活動的に見えるため、症状が軽いと誤解される可能性があります。
しかし、実際には浪費が増えたり、家族に攻撃的になったり、友人との予定を詰め込みすぎて全てキャンセルしたり、暴言を吐いてしまうなど、日常生活に著しい支障が出ている場合が多くあります。
診察時だけでなく、家庭内での「躁状態と思われる行動」を医師に具体的に伝え、それが適切ではない活動であり、周囲に迷惑をかけている状況を申立書などで丁寧に説明することが、適切な評価を受ける上で非常に重要です。
4. 障害年金にはどのような種類があり、どの年金制度に加入していたかによって受給できる等級は異なりますか?
障害年金には主に3種類あり、初診日に加入していた年金制度によって申請する年金と受給できる等級が異なります。
- 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた場合(20歳未満で未加入、アルバイト、自営業、主婦など)。1級または2級に該当し、3級はありません。2級以上で子の加算があります。
- 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた場合(会社員、社会保険加入のアルバイトなど)。1級、2級、3級のいずれかに該当します。2級以上で子・配偶者加算があります。
- 障害共済年金: 初診日に共済年金に加入していた場合(公務員など)。1級、2級、3級のいずれかに該当します。2級以上で子・配偶者加算があります。
5. 双極性感情障害の障害年金申請で、「躁状態」と「うつ状態」の両方を伝えることが重要とされているのはなぜですか?
双極性感情障害は、鬱状態と躁状態を繰り返すことが特徴であり、症状の波が大きいです。
躁状態だけを見ると活動的に見えるため、障害の程度が軽度と判断されてしまう可能性があります。
しかし、実際には躁状態でも日常生活に著しい支障が生じていることが多いため、躁状態と鬱状態それぞれの具体的な困難をバランスよく丁寧に伝えることで、現実的な生活実態が審査側に伝わりやすくなります。
これにより、ガイドライン目安外であっても認定される可能性が高まります。
6. 障害年金申請の際、初診日の証明以外に苦労する点はありますか?
事例では、初診日の特定が困難であったことに加えて、診断書の等級がガイドライン上「目安外」であったことが挙げられています。
診断書上では障害年金の等級に該当しないと判断される場合でも、実際の就労状況(週1~2回の勤務で遅刻・早退・欠勤が多いなど)や日常生活の困難を具体的に伝えることで、総合的な判断で認定を目指す必要があります。
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら
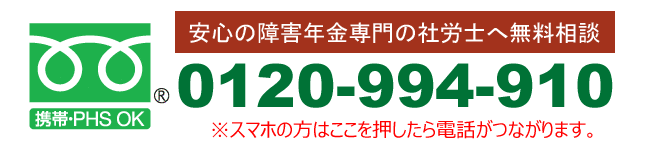
LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。