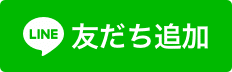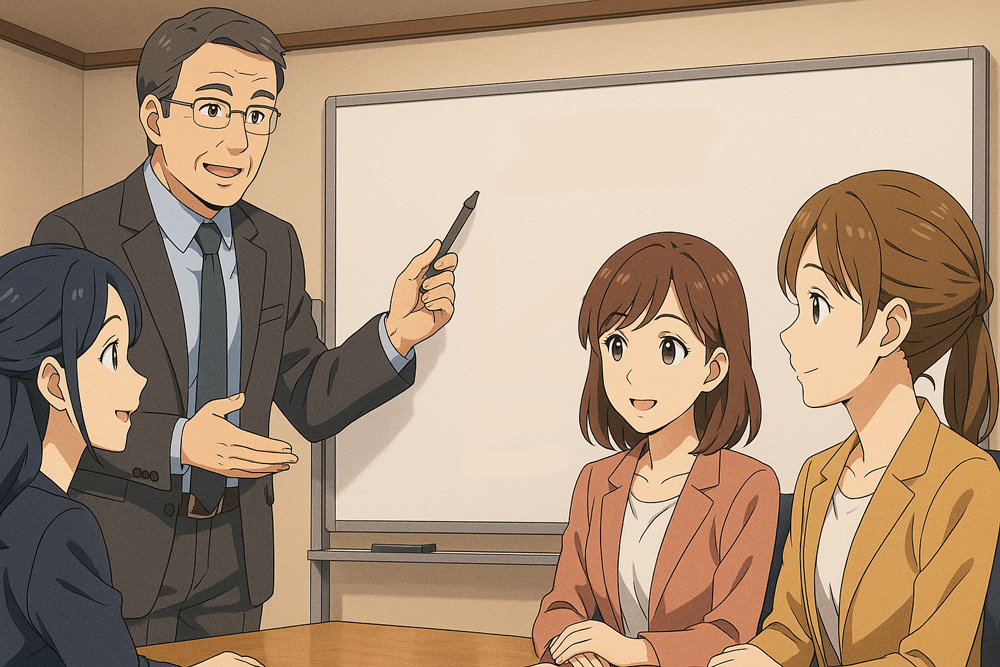
こんにちは。
わくわく社会保険労務士法人の障害年金申請スタッフです。
私たちは定期的に社内で勉強会を開催して、障害年金について勉強しています。
障害年金の請求は非常に複雑ですが、その中でも特に専門家でも判断に迷うことがあるのが「20歳前傷病(はたちまえしょうびょう)」のケースです。
これは、国民年金の加入義務が発生する20歳になる前に初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)がある傷病に関するケースです。
今回は、この「20歳前傷病」の基本的なルールと、見落としがちな「複数の病気がある場合」の複雑な取り扱いについて勉強しましたので、その内容を分かりやすくご紹介したいと思います。
20歳前の知的障害のお子様の今後の障害年金の申請の為の前知識として、また、20歳前傷病でご自身で申請しようと思われている方にも、少しでもお役に立てれば幸いです。
目次
そもそも「20歳前傷病」の障害認定日とは?
障害年金は、原則として「障害認定日」に一定の障害状態にある場合に請求できます。
この障害認定日のルールが、20歳前傷病の場合は通常と異なります。
1. 原則は「20歳の誕生日の前日」
20歳前傷病の場合、障害認定日は原則として「20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)」となります。
例えば、18歳で初診日がある場合でも、1年6ヶ月後の19歳6ヶ月時点ではなく、20歳になるまで待ってから請求手続きを行うのが基本です。
この場合、20歳の誕生日の前後3ヶ月以内の状態を記載した診断書を使用して請求します。
2. 例外:20歳前でも厚生年金に加入していた場合
ただし、20歳前であっても、例えば中学や高校を卒業してすぐに就職し、厚生年金に加入している期間中に初診日がある場合は、「20歳前傷病(障害基礎年金)」の扱いにはなりません。
この場合は、通常の「障害厚生年金」の対象となります。
したがって、20歳を待つ必要はなく、初診日から1年6ヶ月が経過した日(または特例日)が障害認定日となり、その時点から請求が可能です。
20歳前に“複数の傷病”がある場合の落とし穴
ここからが本題です。
20歳前傷病で最も誤解しやすく、手続きを間違えやすいのが、「20歳前に因果関係のない複数の傷病が発生しているケース」です。
20歳前傷病の大原則:「同一の保険事故」として扱う
例えば、生まれつき「知的障害(傷病A)」があり、さらに18歳の時に事故で「足を切断(傷病B)」したとします。この2つの傷病に因果関係はありません。
通常の障害年金であれば、これらは「別々の傷病」として扱われ、それぞれの障害認定日や請求方法(併合など)を検討します。
しかし、20歳前傷病の場合、これらは「同一の保険事故」としてまとめて取り扱われる、という非常に重要なルールがあります。
このルールを知らないと、請求方法を大きく誤る可能性があります。
具体的な3つのケースを見ていきましょう。
ケース1:Aで受給中、Bを追加で請求する(両方20歳認定)
- 状況:
- 傷病A(知的障害)で、20歳時点で障害基礎年金2級を受給中。
- 傷病B(足の切断)も20歳が障害認定日。
- その後、AとBを合わせれば1級に該当する可能性があるため、Bについても請求したい。
- よくある誤解:
- 「Aとは別の病気だから、Bで新規請求(事後重症請求)して、AとBを併合してもらおう」
- 正解:
- これは誤りです。上記の大原則(同一の保険事故)に基づき、この場合のBの請求は「新規請求」ではなく、既に受給しているAの年金に対する「額改定請求(がくかいていせいきゅう)」として扱われます。
- 注意点:
- この場合、通常の額改定のルールが適用されるため、傷病Aの受給権が発生してから1年が経過しないと、Bの診断書を添えた額改定請求はできません。
ケース2:Aが「支給停止中」に、Bで請求する
- 状況:
- ケース1と同様、傷病Aで2級を受給していたが、更新時の診断書で「障害状態が軽くなった」と判断され、年金が「支給停止」になっている。
- その後、傷病B(足の切断)の状態が悪化した(または新たに認定基準に該当した)ため、再度年金受給を目指したい。
- 正解:
- この場合も、Bで新規請求をするのではありません。年金を受ける権利(受給権)自体はAで発生しているため、Bの診断書を添えて「支給停止事由消滅届」として提出します。
ケース3:Aで受給中、B(認定日が20歳以降)を追加で請求する
- 状況:
- これが最も複雑です。
- 傷病A(知的障害)は20歳認定で2級を受給中。
- 傷病B(例:腎臓病)も初診日は19歳ですが、障害認定日(人工透析の開始日)が22歳だったとします。
- 22歳の時点でBの診断書を取得し、Aと合わせて1級を目指す場合。
- 正解:
- この場合、請求者側が「額改定請求書」を提出する必要はありません。
- 傷病Bの診断書を(事後重症請求のように)提出するだけで、年金機構側が「同一の保険事故」であると判断し、「職権(しょっけん)」で等級を1級に改定します。
- 非常に重要な違い:
- 通常の額改定(ケース1)は、「請求した月の翌月」から年金額が変わります。
- しかし、この職権改定(ケース3)の場合は、「Bの診断書の現症日(診断書に書かれた日付)の翌月」から改定されます。
- つまり、診断書の日付が数ヶ月前のものであれば、提出が遅れたとしても、その分を遡って1級との差額が支給される可能性があるのです。
まとめ
「20歳前傷病」は、保険料の納付要件が問われない(所得制限はあります)代わりに、上記のような独自の複雑なルールが存在します。
- 20歳前に複数の傷病がある場合は「同一の保険事故」として扱われる。
- 「併合認定」ではなく「額改定請求」や「職権改定」になるケースが多い。
- 20歳前でも厚生年金加入中なら通常の障害厚生年金となる。
これらのルールは非常に専門的であり、請求方法を間違えると、本来受け取れるはずの年金が受け取れなくなったり、受給開始が遅れたりする可能性があります。
ご自身のケースがどれに該当するのか、どのように手続きを進めればよいか不安な場合は、ぜひ一度、障害年金を専門とする私たち社会保険労務士にご相談ください。
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。
お電話での無料相談はこちら
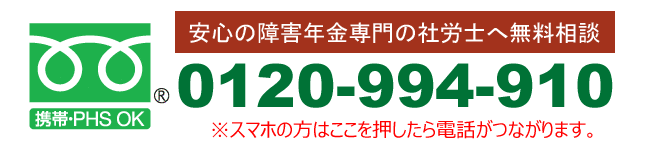
LINE@での無料相談はこちら
当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。